「私は日本で育った雑草」
38年、ベネズエラに生きた日本人女性画家の驚くべき人生
38年、ベネズエラに生きた日本人女性画家の驚くべき人生
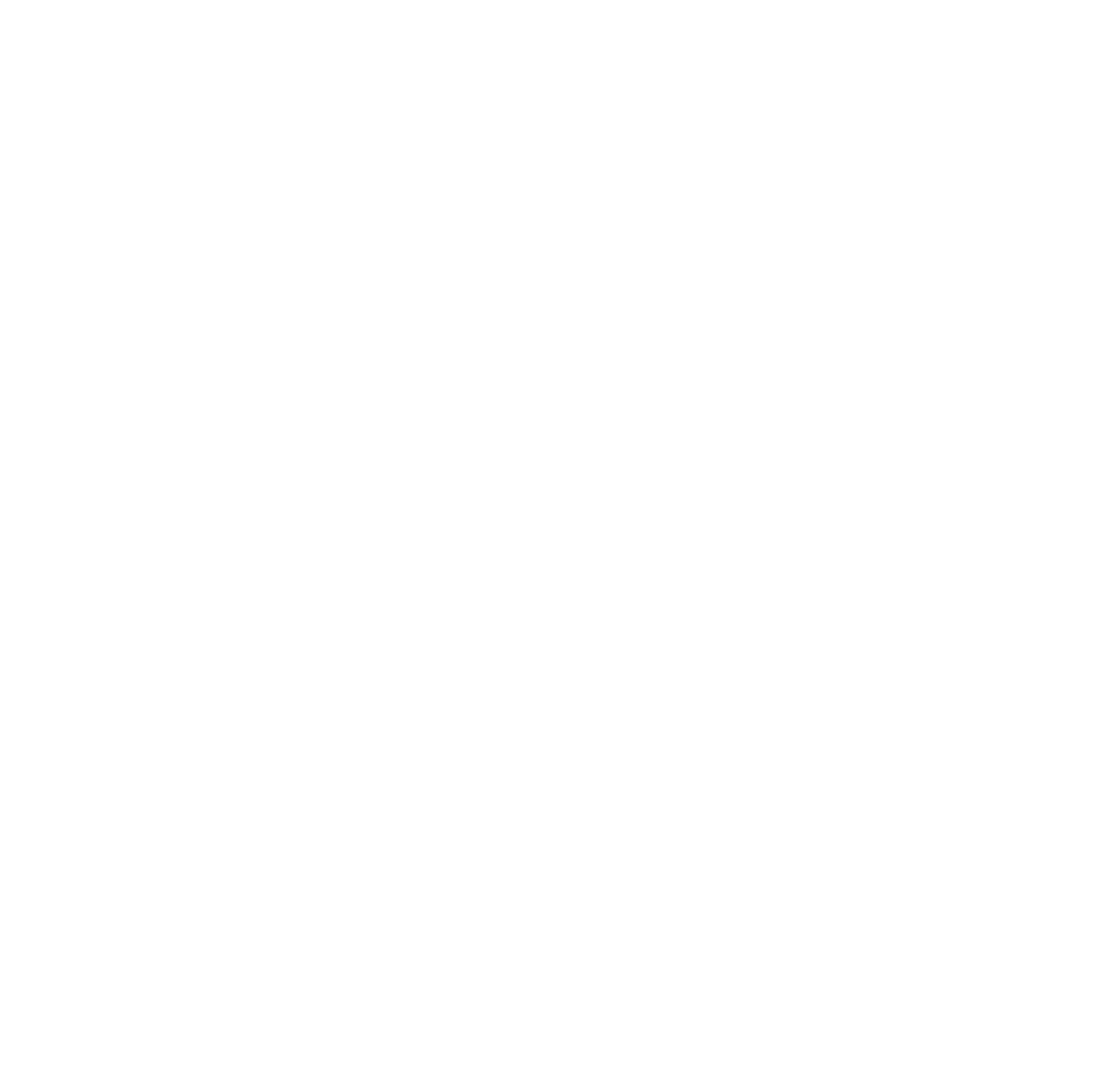
1977年、当時、うら若かった小谷孝子さんは一大決心をした。愛する夫のあとについて、ほぼ世界の果ての国、ベネズエラに行こうと。それから38年が過ぎ、小谷さんは自分の祖国、日本に戻ると、再びラテンアメリカに戻ることができなくなった。こうして小谷さんは祖国日本で生活し、創作することになった。小谷さんはスプートニクからの取材にベネズエラの人たちに折り紙を伝えた経緯や、ペースト状のたばこを使って東西の芸術を融合させたこと、そしてなぜ自分を浦島花子と思うのかについて語ってくれた。
初の個展を開くのに、私の場合20年近くかかったの
「名もない人間がベネズエラに行って、そこで根を張って花を咲かせた。」
画家、小谷孝子さんはご自分のお話をこのセリフから始めた。40年以上も前、米国留学を終えた夫と共に彼の祖国、ベネズエラに移住した。小谷さんはスペイン語を全く話せないままに、当時、ラテンアメリカの中でも最も豊かで安定した国に数えられていたベネズエラに渡ったのだった。
«
「日本と米国は殆ど同じでしょう。でもべネズエラはいろんなことが違う。言葉から食べる物、人の性格、交通の渋滞…。みんな大きな声でしゃべっているけど、私、言葉わからないから、怒っているように聞こえて。最初は大変でした。」小谷さんは自分は一体どこに行くのか、全くわかっていなかったと当時を振り返った。
»
小谷さんは日本にいるときから絵を描くのが本当に好きだった。だが健康上の理由から、絵描きを職業にするのはあきらめざるを得なかった。戦後の大阪の闇市で購入した牛乳がもとで、幼い小谷さんも母親も共に結核を病んでしまったのだ。
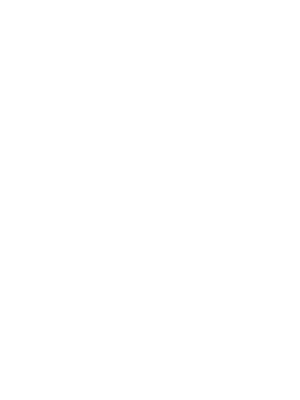
ベネズエラで小谷さんはすぐに仕事を見つけたが、それは絵とは全く関係のない職種だった。小谷さんが本格的に絵を描くきっかけとなったのは家族の悲劇だった。
ベネズエラで小谷さんはすぐに仕事を見つけたが、それは絵とは全く関係のない職種だった。小谷さんが本格的に絵を描くきっかけとなったのは家族の悲劇だった。
«
「結婚した時はまだ若いからお金もなかったので働き始めたけれど、子どもが小さかったとき大変で、手伝ってもらおうとカラカスへ母を呼んだの。だけど、労うために行った旅行の帰り道で交通事故に遭って母が亡くなったんです。すごいショックで辛くて、3年くらい本当に何もできませんでした。でもある日気が付いて、私が苦しんで泣いている様子を母が上から見たらもっと悲しむだろうと思った。私が死んで、母が生き残ったら、子どもたちはもっと苦しいでしょう。母は私が死なないように身代わりになって死んだんだとわかった。それからと思って立ち上がって。私が幸せにならなかったら、母はとても辛いはず。そして私が幸せになるためには、したいことをしないといけないと思ったのね。」
»
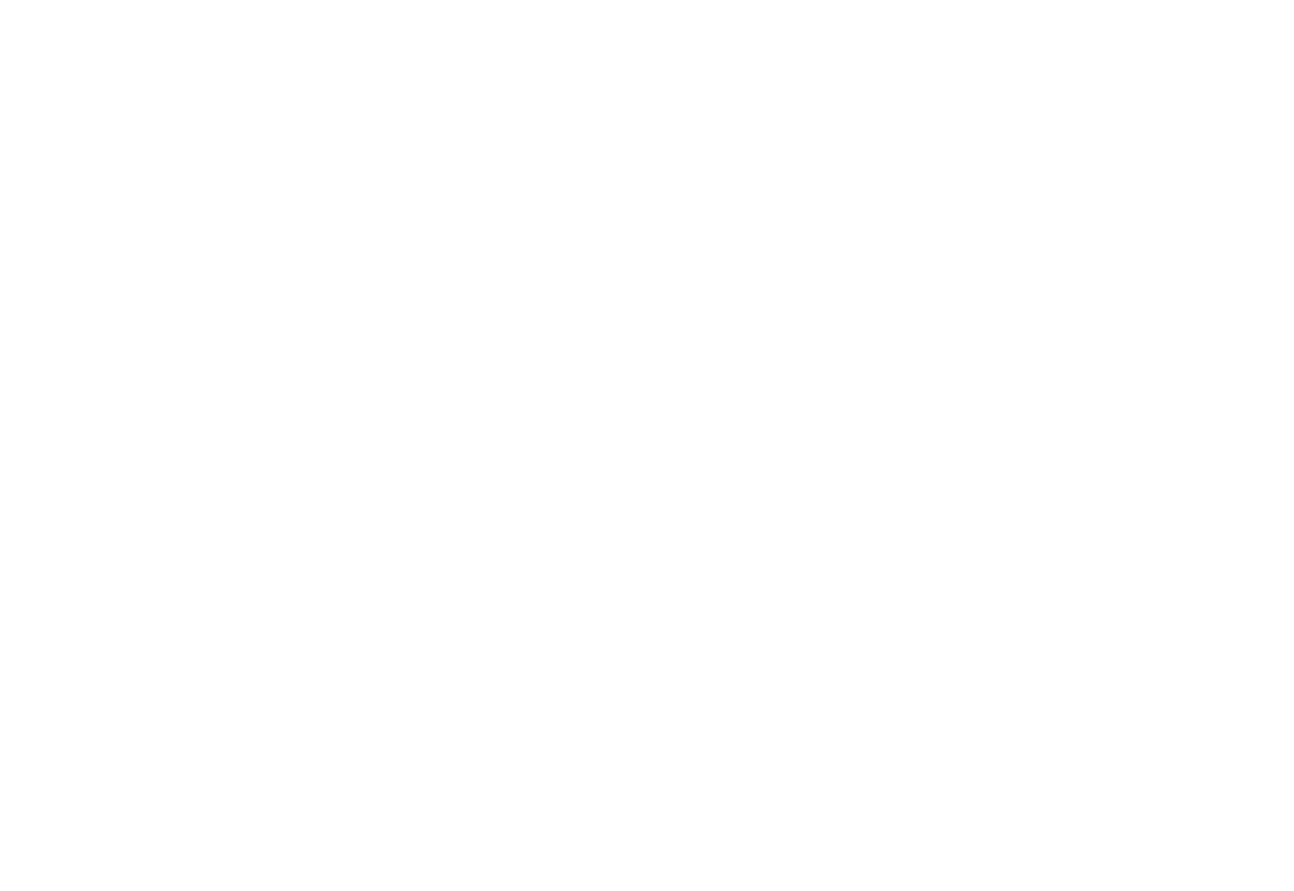
40歳で初めて本格的に絵の勉強を開始。その18年後に初の個展を開いた。
「いろんな先生について、下手くそと言われながら。とってもいい先生に出会うことが出来て、その人が引っ張ってくれた。『なんで描いたんだ』とか、『素人』とか貶されて、泣きながらもついていったのね。「続けろよ、お前は何かを持っているよ」と言われて、頑張って続けて、やっと個展をしたのが2006年でした。20年近くかかったかな。」
「いろんな先生について、下手くそと言われながら。とってもいい先生に出会うことが出来て、その人が引っ張ってくれた。『なんで描いたんだ』とか、『素人』とか貶されて、泣きながらもついていったのね。「続けろよ、お前は何かを持っているよ」と言われて、頑張って続けて、やっと個展をしたのが2006年でした。20年近くかかったかな。」
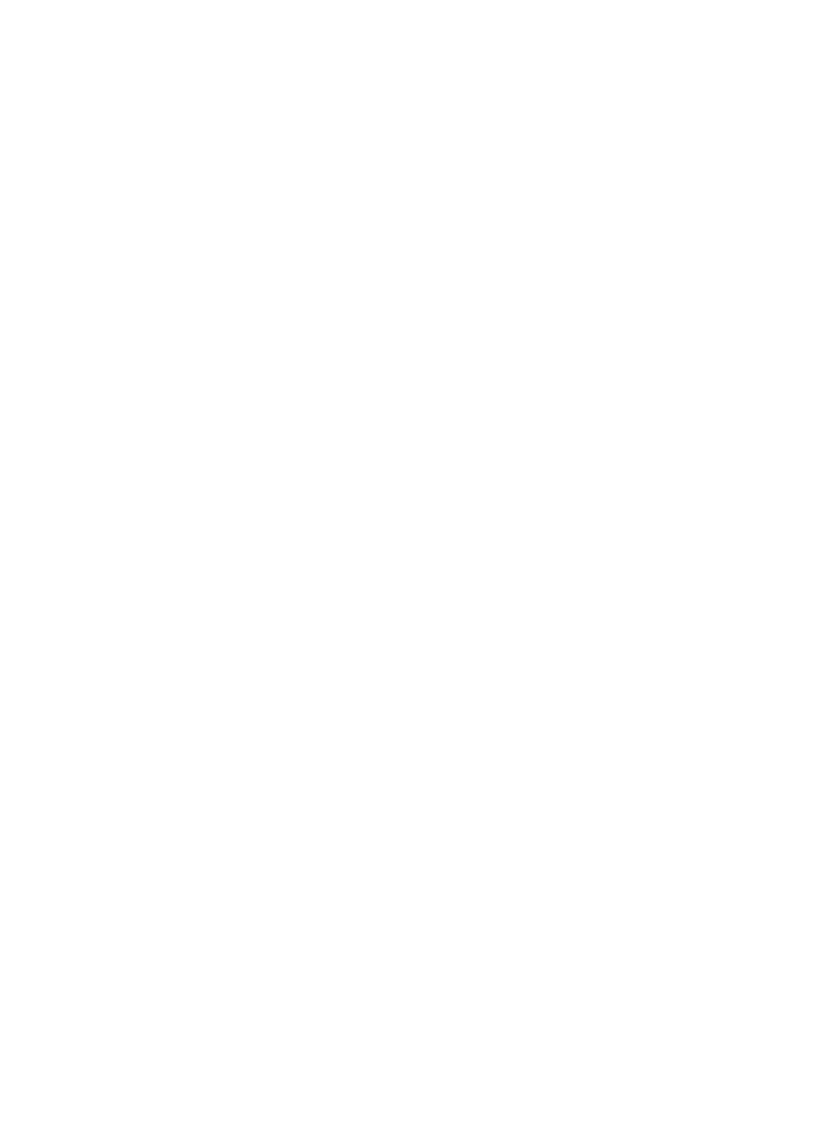
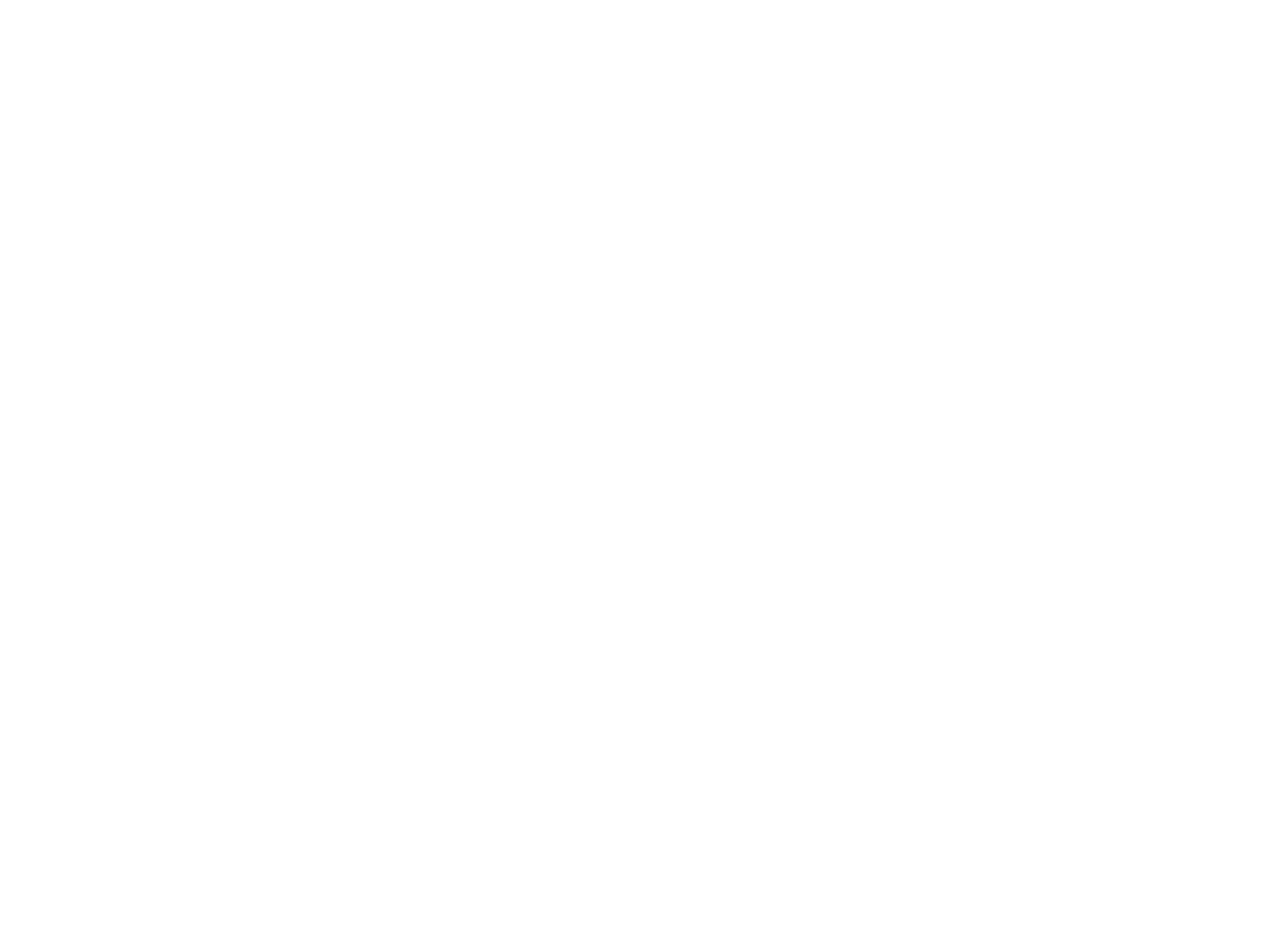
華の韻
この時から小谷さんはほぼ毎年グループの展覧会や個展に参加するようになった。小谷さんの絵は日本、マイアミ、ワシントン、ニューヨーク、ドレスデン、ミラノで展覧され、多くの人の感嘆を呼んだ。それでも小谷さんが一番印象深かったのはカラカスで初めて行った個展「華の韻」だったという。
この時から小谷さんはほぼ毎年グループの展覧会や個展に参加するようになった。小谷さんの絵は日本、マイアミ、ワシントン、ニューヨーク、ドレスデン、ミラノで展覧され、多くの人の感嘆を呼んだ。それでも小谷さんが一番印象深かったのはカラカスで初めて行った個展「華の韻」だったという。
小谷さんの描く花たちは庭や野原に咲くものではない。
「何を描くかを考えないで遊ぶというか。描いているに、あぁ、これはおもしろいね、というのが増えてきて、そこからどんどん進むから、描こうと思っては絶対に描けないんですよ。その時の気分とムードとそこから出てきたものを見ながら、あぁ、これは家族の歴史だなとか、愛、繁栄とか、そういうのになる。バラのような具体的な花ももちろん描けますけど描かないわけ」。
「何を描くかを考えないで遊ぶというか。描いているに、あぁ、これはおもしろいね、というのが増えてきて、そこからどんどん進むから、描こうと思っては絶対に描けないんですよ。その時の気分とムードとそこから出てきたものを見ながら、あぁ、これは家族の歴史だなとか、愛、繁栄とか、そういうのになる。バラのような具体的な花ももちろん描けますけど描かないわけ」。
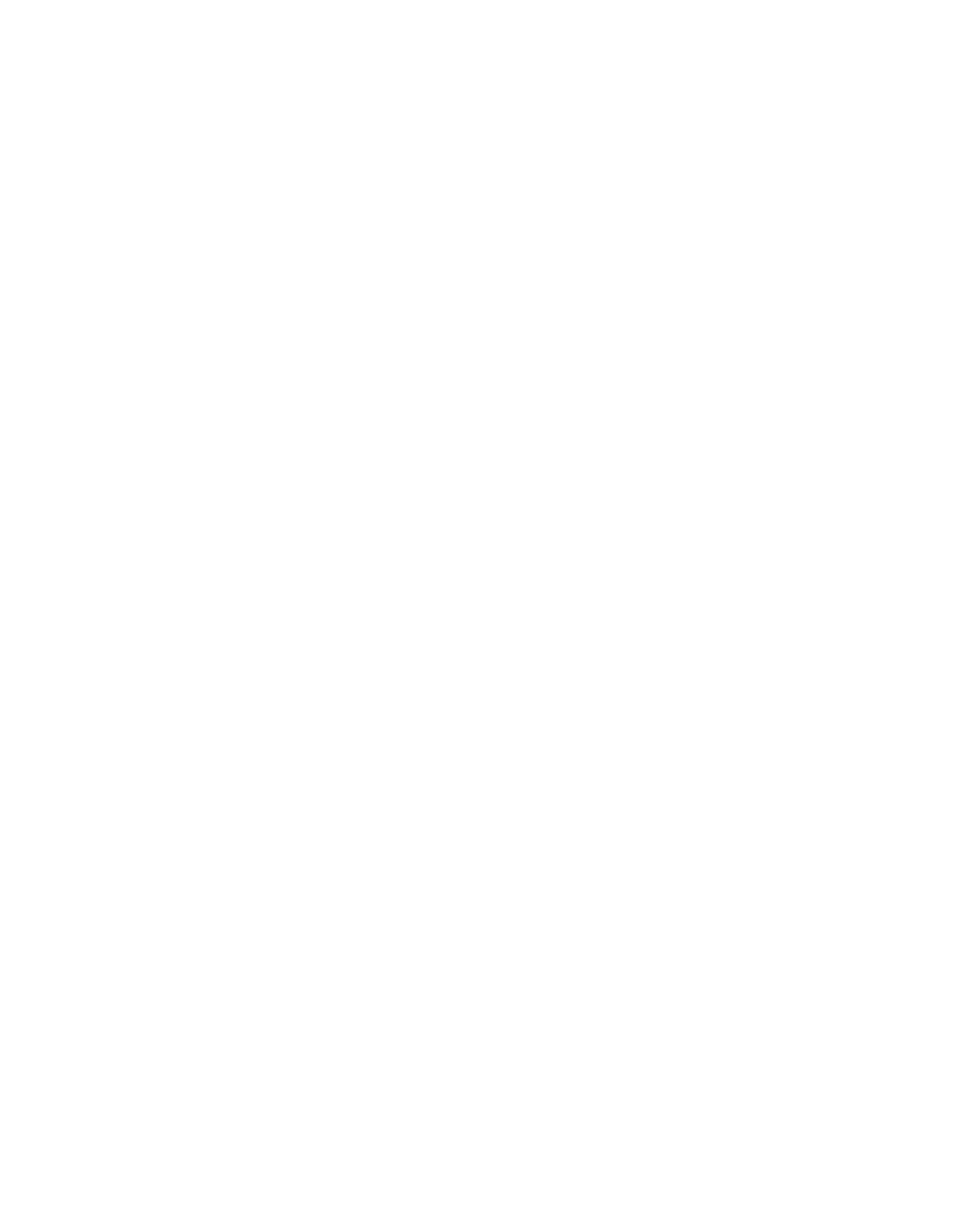 | 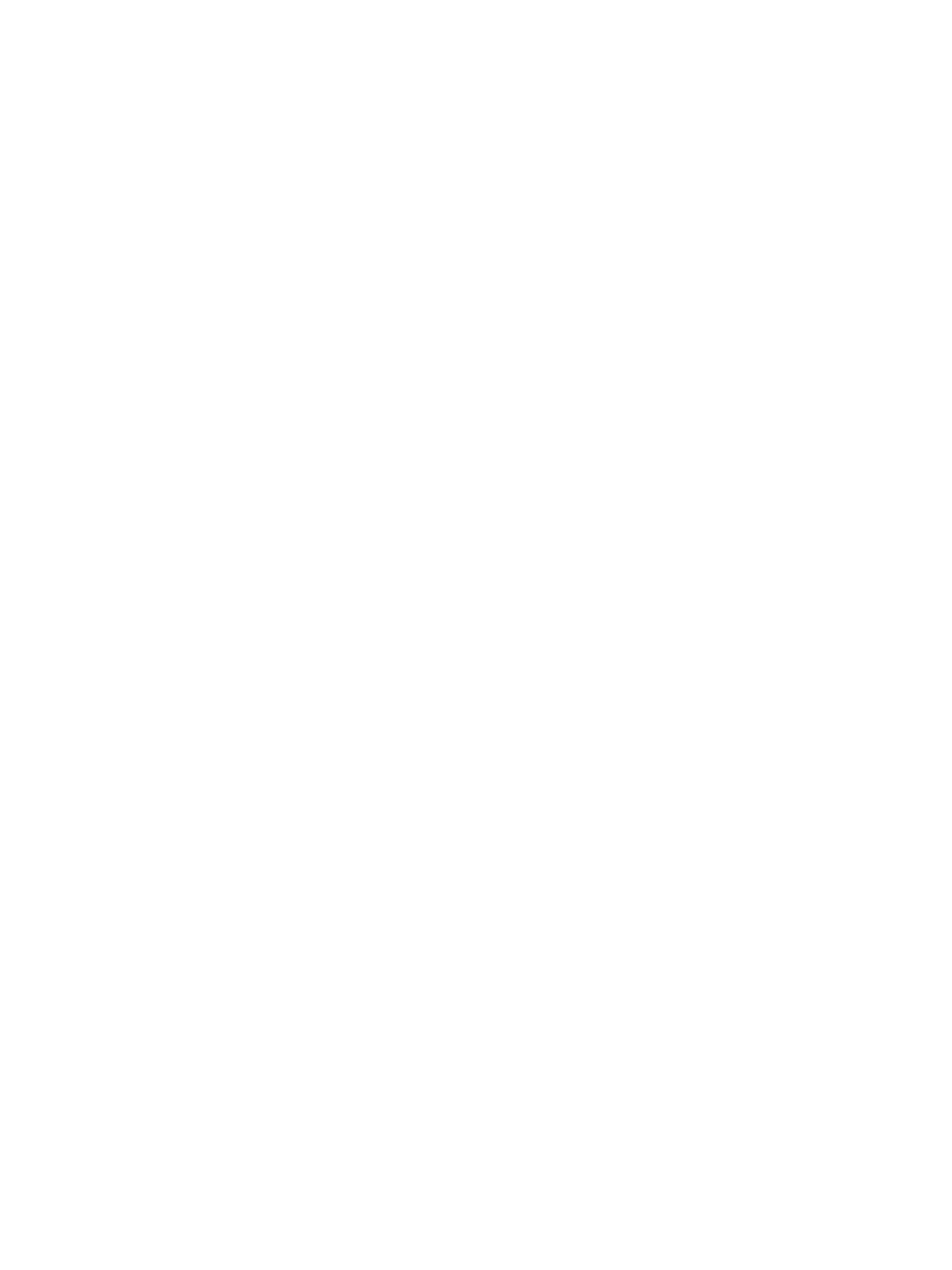 | 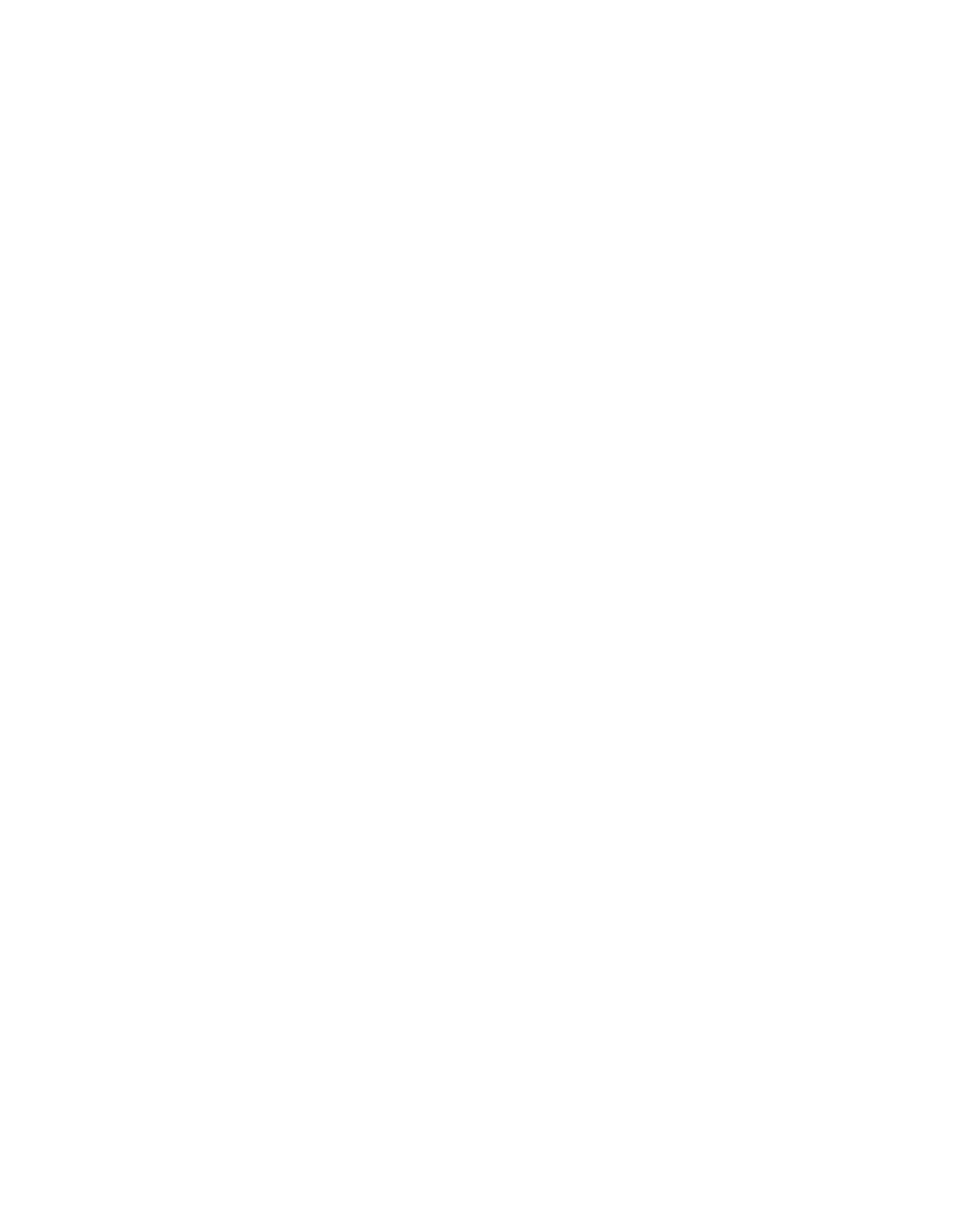 |
ほかの作品でもそうだが、この花たちの中で小谷 さんは東と西をひとつに合わせている。小谷さんが用いるのは普通の絵の具ではなく、日本の墨とベネズエラの「チモ」というペースト状のたばこだ。
「チモはすごい強いんですよ。向こうの人たちはこれを口が真っ黒になるくらい噛むんです。絵を描いている人の作品を地方のお土産屋さんで見て、『これは何?』と聞いたら、『チモだよ』と言われて。これからすごくいい茶色の色がでるんですよ。もっと濃い、すごく面白い色が出るのね。これが使えないかなと思って。それと日本の墨。チモは油性、墨は水性でしょ。ぱっとはじくんです。それがすごく面白くて夢中になってたくさん描いたのね。東洋と西洋が交わるというか。それがものすごく気に入って」。
小谷さんは時に手でくしゃくしゃに皺を寄せた和紙に描く。和紙の皺の中でチモと墨は新たな、えも言えぬ色を得る。そして絵は全く別の姿になる。
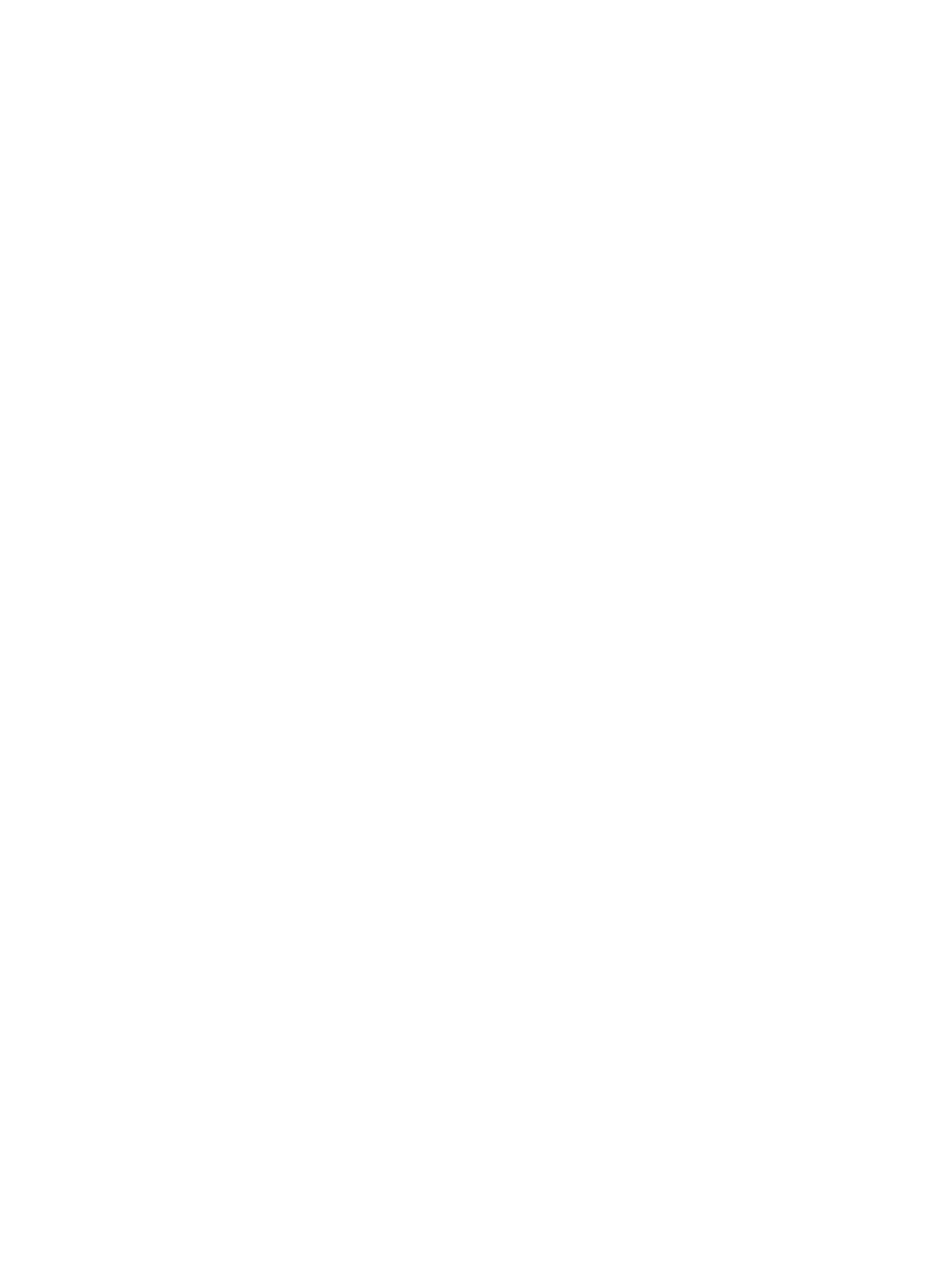
«
「私の絵は何かを見てきれいに描くものではないのね。もちろん描けと言われたら描けるけれど、それではちょっと満足できないっていうのかな。心から湧き出る人の気持ち。たとえば私は女性の顔をよく描くんだけど、人は目を見ると幸せか、悲しいか、辛いことがあるかわかるでしょう。それを表現したい。すごく難しいことなんだけど、めったに起こらないんだけど、何も考えず、自分を忘れて描いている時に、あっ、この線とかこの色というのが時々出るわけ」。
»
「折り紙の母」
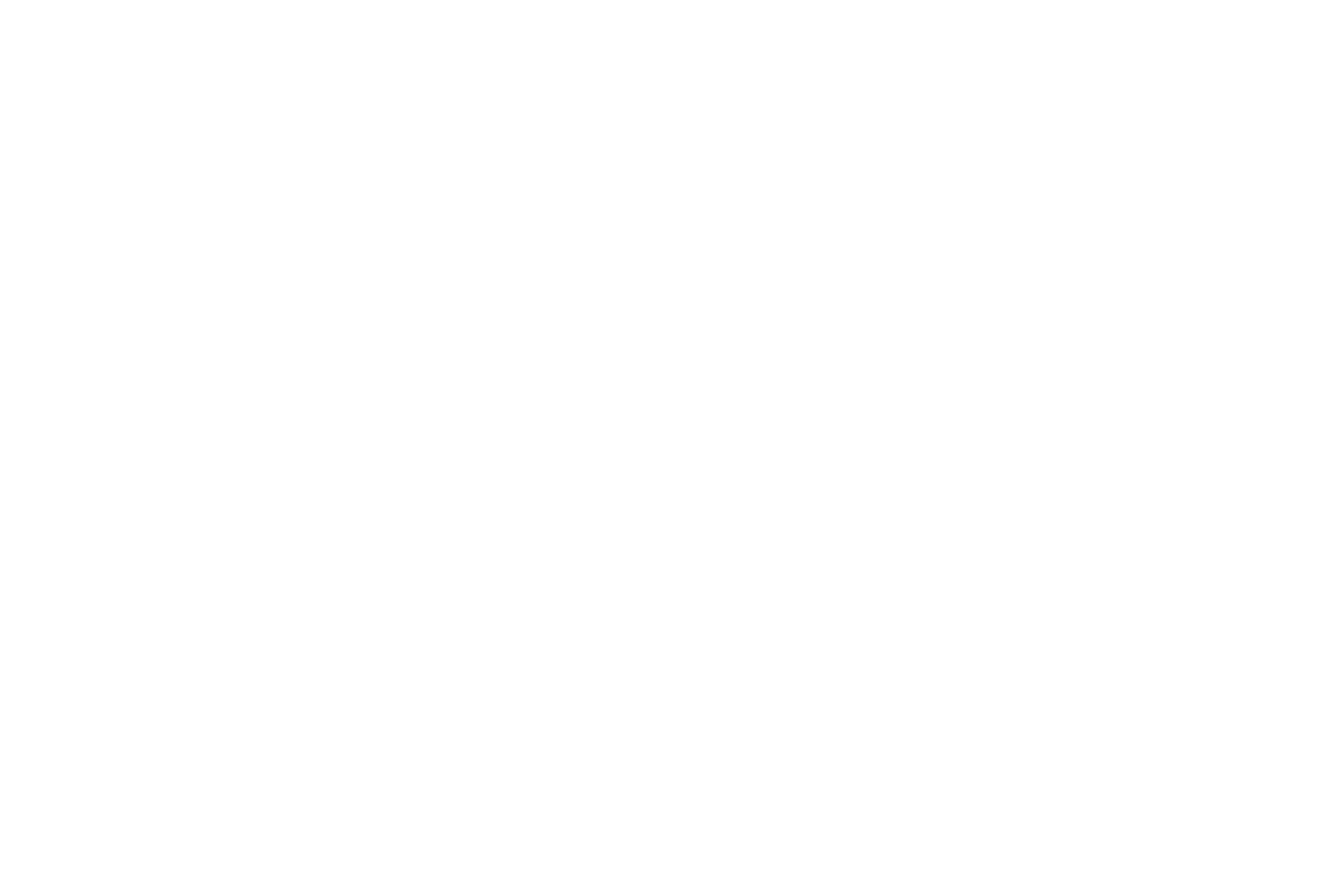
2018年、ベネズエラ折り紙協会は30周年を祝い、展覧会、各地で講習会を行い、大勢のの参加者を集めた。ベネズエラに折り紙が普及するきっかけとなったのは小谷さんが娘の通う幼稚園で始めた折り紙教室だった。子供が毎日持って帰るのは、花とかアヒル等のぬり絵ばかりで、自分が日本での受けた教育とは全然違い、これでは創造性がつかないと思ったので、子どもたちに折り紙を教えたいと申し出た。折り紙は紙さえあればできるからだ。
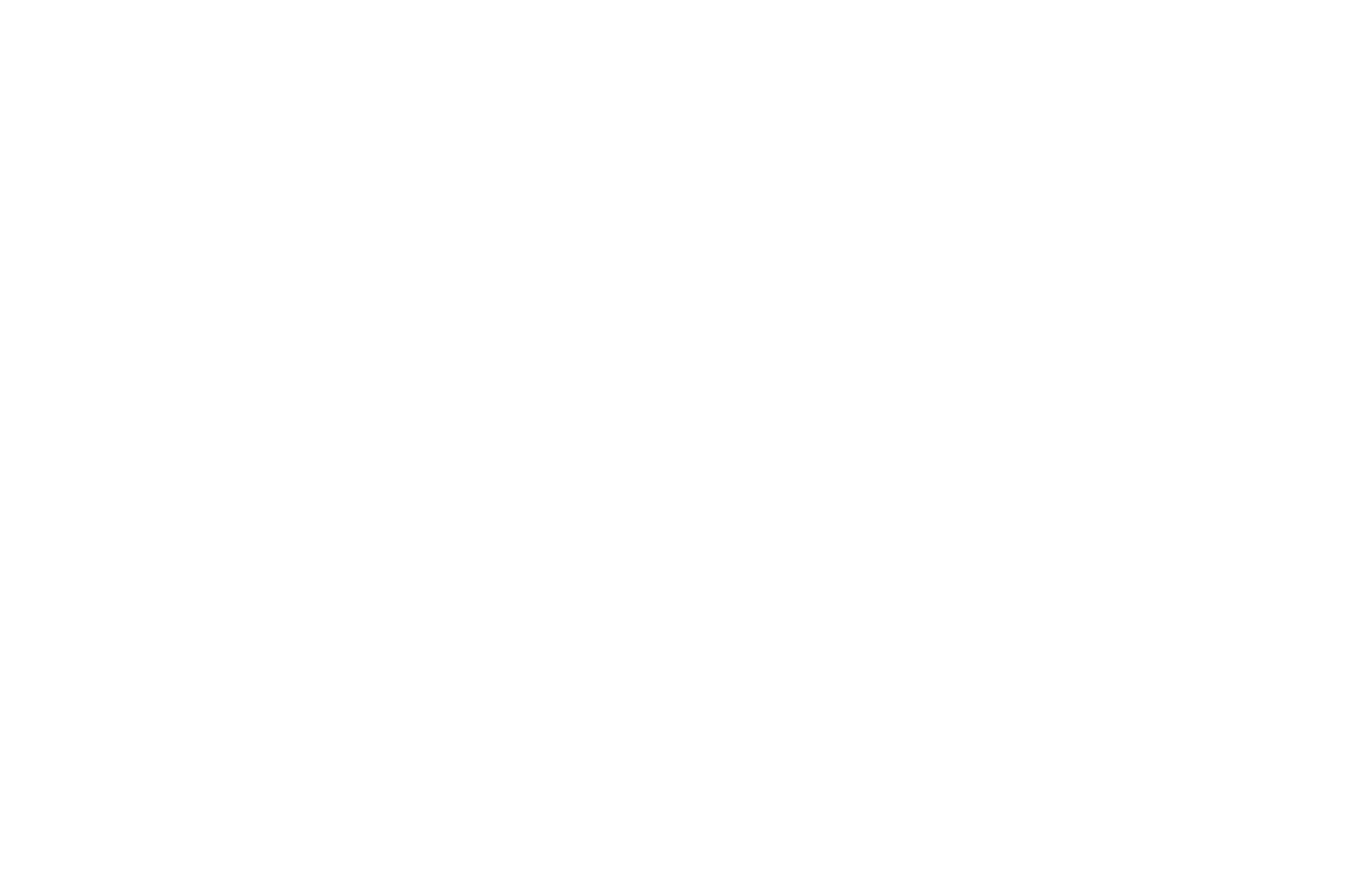
子どもたちはすぐさま折り紙を覚え、人気を博した。それならもっと多くのベネズエラの子供達に折り紙の楽しみを知ってもらおうと、カラカス子供博物館や児童基金で教えた。そして小谷さんはさらに先に進み、折り紙協会を創設した。折り紙に魅せられた人の数はどんどんと増えていき、協会のメンバーと共にベネズエラのあちらこちらで展覧会や講習会を組織するようになり、ジャングルの中の先住民の住む部落、グランサバナにまで足を運んだ。
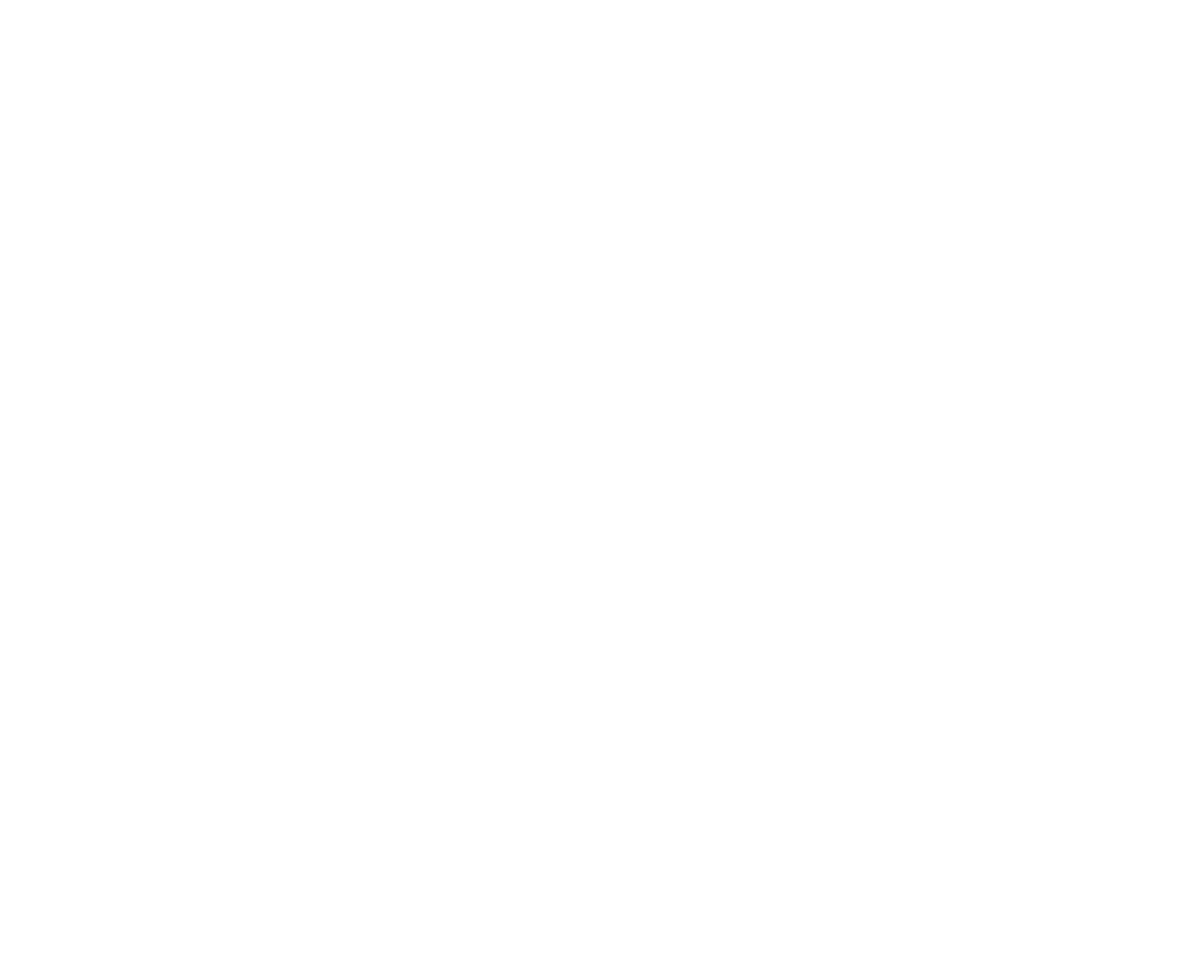
ぺモン族の間で使われているのは地元特有の言語だった。小谷さんは最初、共通言語を見出すことも難しかったという。ところが普通の紙から花、動物を折り始めると、みんなが家から出てきて小谷さんの周りに座り、その手から生まれる魔法に我を忘れてじっと見入った。こうして小谷さんは皆に「折り紙の母」と呼ばれるようになった。
浦島花子
«
「2014年頃から石油の値段が下がったでしょう。1バレル100ドルくらいだったのがだいぶ下がった時にドルが無くなって。石油で物を買っていた国だから、自分で物を作ったりしなくてもよかった。でも入る物が無くなったから買えなくなったんだね。それから物が無くなりました。2014年頃から食べる物、薬が手に入らなくなり本当に大変でした。」
»
2016年、小谷さんは日本行きのチケットを買った。ベネズエラの容易ではない生活から少しの間離れるつもりだったのだが、元に戻ることはできなくなってしまった。「can't come back」小谷さんは短くこう言った。こうして38年間、日本の外に暮らした小谷さんは再び祖国に戻った。ところが小谷さん自身が全くの別人になっていた。
「私はもちろん日本人。生まれて育って教育を受けたわけだけど、人生の3分の2くらい外国に住むと、100%日本人ではなくなって、違う目で見てしまうのね。それは当たり前でみんなそうだと思うの。だから帰ってきてもう一回日本人になれるかっていったらそうじゃないのね。だから浦島花子さんになったような気分がします」。
小谷さんは絵を描き、個展を開き、日本人に自分の好きなベネズエラのことを語り続けている。小谷さんがベネズエラに残してきたのは家族や友人だけではない。小谷さんの心の一部もベネズエラとともにある。
関連記事
