スプートニク日本
大人気ドラマ「チェルノブイリ」に黒人俳優がいないと憤慨した視聴者の声により、本物の黒人事故処理員が見つかった!
イーゴリ・ヒリャクのインタビュー
イーゴリ・ヒリャクのインタビュー
米国のテレビ局HBOと英国のテレビネットワーク「スカイ」が共同制作したドラマ「チェルノブイリ」が今年5月に放送されてから、、1986年4月26日のチェルノブイリ原発事故はかつてない大きな関心を世界中から集めた。このドラマシリーズは、「ゲーム・オブ・スローンズ」の視聴率をも凌ぐ人気を博し、視聴者は30年前の大事故にくぎ付けになっただけでなく、放射性物質の「塊」が溶解するのを阻止しようとした英雄たちの生涯にも注目した。学者、運転技師、消防士、軍のリクビダートル(事故処理員)、その誰もが命がけだった。
このドラマが史実に基づいたものであるかどうかは、放送直後から論争になった。様々な細部が「史実と違う」と指摘されたため、制作側は「これはドキュメンタリーではなく創作である」と弁解するはめになった。そもそも出演しているのはウクライナのアクセントをもつ白人ではなくて、英国人であるので、史実を全く忠実にたどるわけにはいかない。そこで英国の視聴者のひとり、カルラ・メリー・スミットは、「それならなぜ、黒人俳優を起用しなかったのか?」とツイートした。ツイートは炎上し、「当時のチェルノブイリに黒人などいたはずがない」とネット社会の批判と冷笑を呼んだ。しかしそんな炎上騒ぎの中、なんと黒人リクビダートルの存在が明らかになった。それは、現在ロシアのチェレポヴェツ市に暮らすイーゴリ・ヒリャク。彼がチェルノブイリの事故現場で瓦礫撤去作業に当たっていた際の写真がネットに流出したのだ。そこでネットはまた騒然となり、わずか数日で各局の取材が「新たな」主役に殺到した。
イーゴリ・ヒリャクはかつてチェルノブイリ事故現場でリクビダートルとして作業に当たった経歴を持ち、外見は黒人である。イーゴリはロシア人とウクライナ人の家庭に生まれたが、母方の遠い先祖の血が隔世遺伝して肌が黒くなったようだ、と話す。イーゴリはスプートニクのインタビューに応じ、死の灰を巻き上げる原子炉からわずか100メートルの距離で作業に当たったことや、当時の日常生活、彼が目にした様々な英雄についても話をしてくれた。
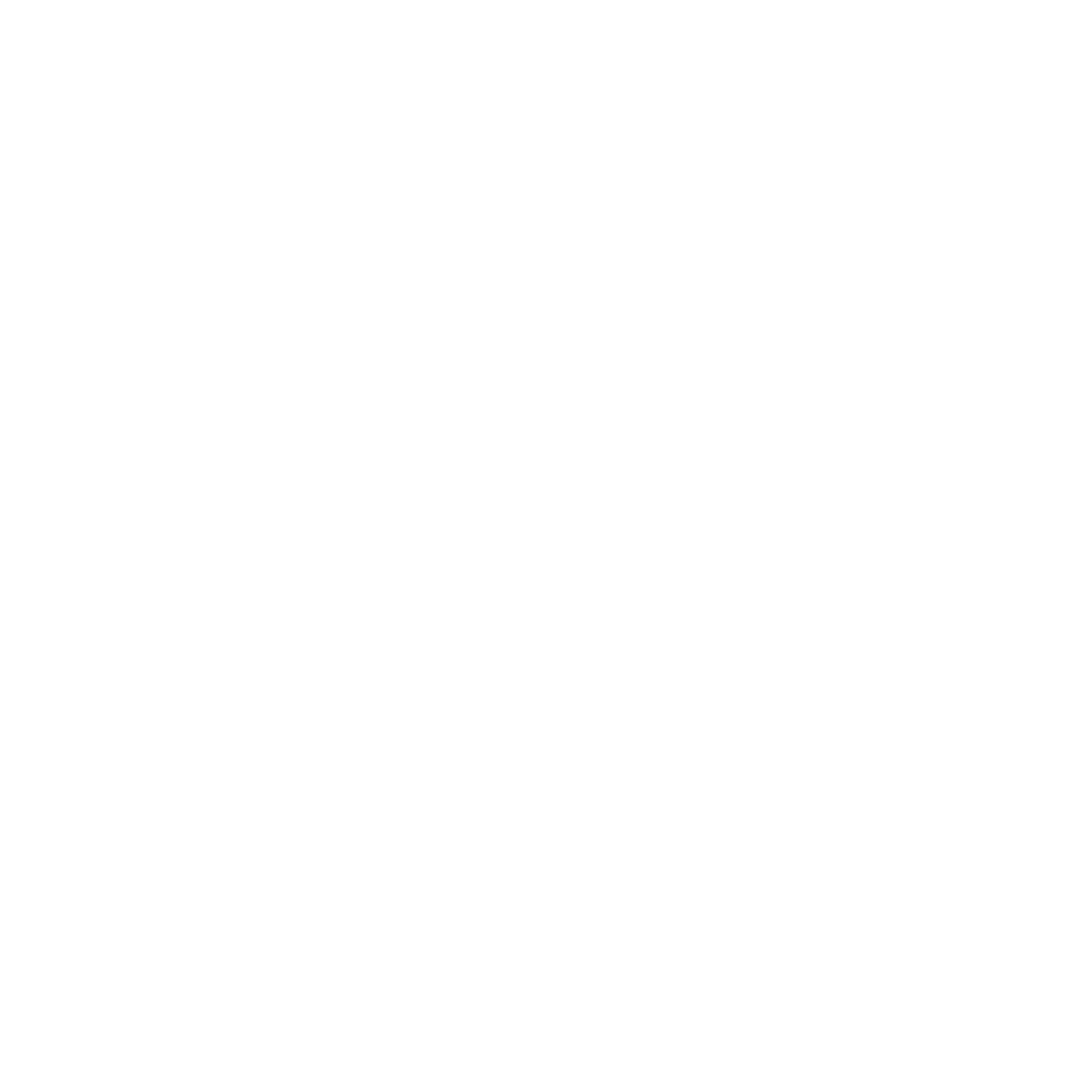
イーゴリ・ヒリャクさん
「恐怖心はなかった」
当時19歳だったイーゴリ・ヒリャクが現場に投入されたのは原子炉の爆発から2日目のことだった。当時、キエフで兵役中だったイーゴリも出動を命じられた。駐屯地を離れたイーゴリや同じ隊の仲間は、自分がどこへ向かうのか、知る由もなかった。命令では「訓練」としか伝えられなかったのだ。 イーゴリ曰く、当時19歳だった彼も危険は承知していた。
「私は勉強がそれなりにできたので、軍事演習の内容にも関心を持っていた。そして原子力エネルギーの危険は戦争に匹敵することを理解していた。その危険は承知していた。もちろん、一抹の不安はあった。しかし、恐怖心はなかった。作業をしなくては、という考えでいっぱいだったし、誰しも作業に追われていた」
イーゴリや同じ隊の仲間に下された最初の指令は、ウクライナとの国境近くに暮らすベラルーシの村民たちを疎開させるため、プリピャチ川に橋渡しをすることだった。その後、原子炉近くでの任務が彼を待っていた。イーゴリは約100メートルの距離まで接近し、高さ3メートルの瓦礫撤去作業に取り掛かった。
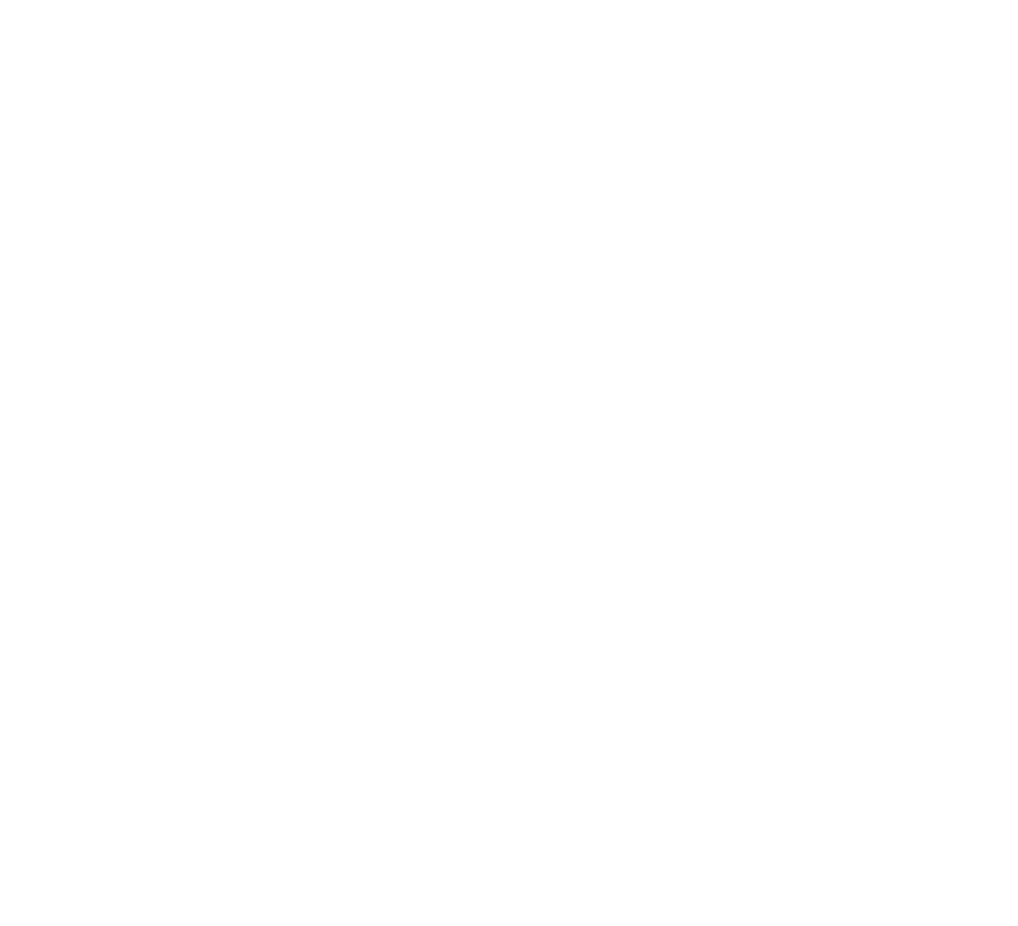
「25レントゲンまで」勤務可
最初の数日間、リクビダートルは防護服とガスマスクを装着していた。その後、原発の作業員と相談し、軍服と一般的なマスクの装着で勤務が認められた。
「気温25度の中、防護服姿で作業するのは暑かった。ジトジトしていて汗だく。防護服の中も、ガスマスクの中も汗が溜まってしまって、息もできなかった。そんな状態で作業は一日続いた」
建屋内での作業になると、原発の作業員が着用していたものと同じ白の防護服が支給された。
「防護服の入った箱が山ほど送られてきた。一度着用した防護服はシャワーを浴びる前に回収された。そしてシャワーを浴びると、新しい防護服が支給された」
そうした防護服で安全面に支障はなかったのだろうか。イーゴリは十分だったと考えている。また、イーゴリは事故を扱った番組の撮影に参加した際、原発で勤務していた研究者らに意見を聞いたそうだが、こうした研究者らも同じく安全面に問題はなかったと考えていたようだ。
作業員の健康チェックは専門の医師が行っていた。被爆症状が出た作業員には、核戦争の際に服用する目的で軍が開発したヨウ素の錠剤が支給された。しかし、被爆の線量計はされなかったとイーゴリは証言している。 正確な情報もないまま、作業員ノートには「1日あたり0.1から0.2レントゲンの被爆」と記された。そして被爆量が25レントゲンに達すると、帰還を命じられた。
青春は謳歌した
原発から半径30キロの避難地域にあるプリピャチ市に足を踏み入れたのは、事故から一か月後のことだった。事故前、この街には約4万9000人以上が暮らしており、住民の平均年齢は26歳だった。その街がなんと無人状態と化していた。
「 その光景を前に、背筋が凍った。誰もいない森に入るのとはわけが違う。無人の街に滞在して、気分がいいはずがない」
もちろん、避難地域だったとはいえ、隊員らは作業時間外ともなれば、そこはやはり若者で、めいめいに趣味の時間を楽しんだ。
「 普段の野戦訓練時となにも変わらない時間だった。ふざけたり、暇つぶしを探したりした。例えば、非番の日はみんなでテレビ番組を見たし、夕方になれば、こっそりサッカーの試合を見て盛り上がった」
ただし、飲酒は許されなかった。ドラマでは兵隊にウォッカの箱がこれでもかと配給されるシーンがあるが、実際にそんなことは無かったという。
「 そんなことは言語道断。仮に飲酒して発覚すれば、厳罰が下されたに違いない。隊の誰一人として、そんなことは考えもしなかった」
「あくまでドラマの話」
事実考証で甘い点はいくつもあったにせよ、イーゴリは『チェルノブイリ』そのものを高く評価し、撮影班は「全力を尽くした」として、その苦労をねぎらった。仮に考証の甘さが気になるとすれば、あくまでドラマの話なのだから、目くじらを立てる必要はないと語った。ドラマの事実考証は6割がた正しいとした。
ドラマの中では、レガソフ博士がドイツ製の「ルノホート」(遠隔操作ロボ)を試すものの、失敗に終わるシーンがある。そこで博士は「バイオロボ」(つまりは人間)の投入を提案する。この点に関してイーゴリは司令官がリクビダートルをモノ扱いすることはなかったとコメントしている。
ドラマの中では、レガソフ博士がドイツ製の「ルノホート」(遠隔操作ロボ)を試すものの、失敗に終わるシーンがある。そこで博士は「バイオロボ」(つまりは人間)の投入を提案する。この点に関してイーゴリは司令官がリクビダートルをモノ扱いすることはなかったとコメントしている。
「司令官は常に一緒にいたし、同じ作業に当たっていた。誰か一人が安全な場所にいて、そこから指示するという状況ではなかった」
事故発生後の数日間、新たな爆発を防ぐため、核燃料が溶け落ちたプールの中に潜水士らが入り、水を汲み出す作業にあたった。イーゴリはこうした潜水士を「レジェンド」と呼んでいる。イーゴリは「彼らと肩を並べていると、心臓が高鳴った」と語り、テレビや新聞でしか見たことのない潜水士らとの面会を回想した。ただし、イーゴリ自身はそういった特殊任務に就いたことはなく、自分を「レジェンド」の一員とは思っていないようだ。
写真:Sputnik / Igor Kostine
チェルノブイリ原子力発電所で発生した原子力事故ではソ連全土から60万人以上の人々が動員され、事故処理作業に当たった。歴史に名を残したのは、そのうちの数十名に過ぎないが、60万人のうち、一人一人がこの途方もない作業に従事したことは忘れるべきではない。

